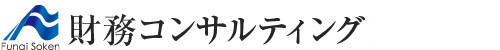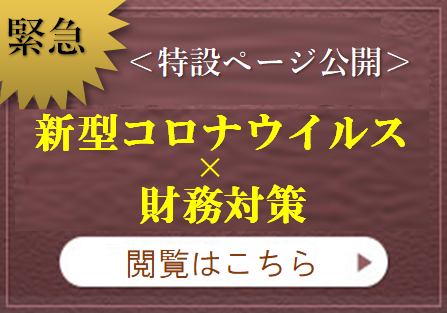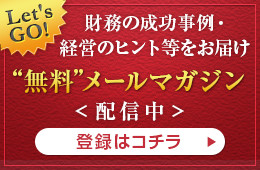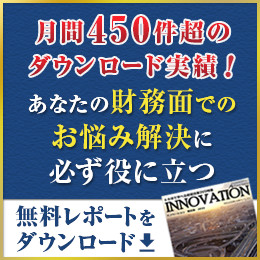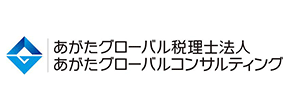中小企業が実践している 企業成長に向けた攻めのホールディングス化(1)
- 最終更新日/

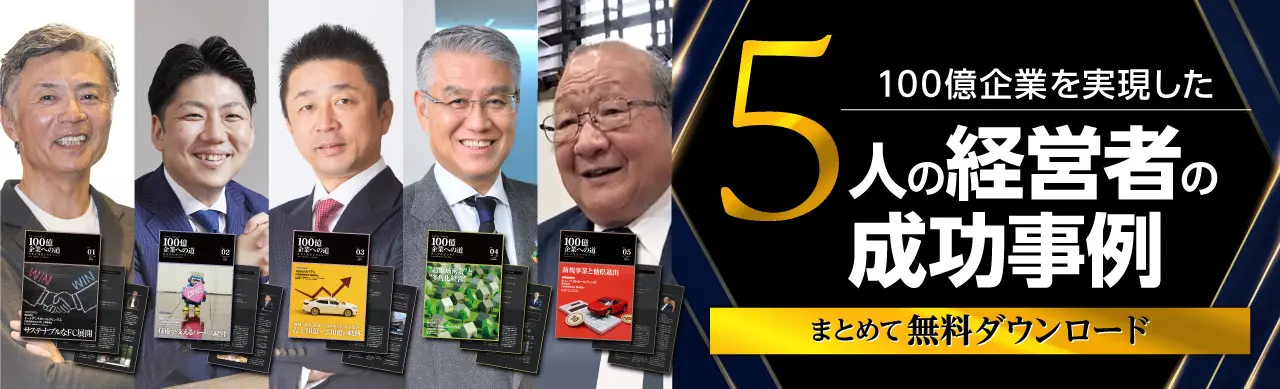
「○○会社が○○ホールディングスを設立した」と耳にしたことはありませんか?
このコラムをご覧くださっている皆様の中には、ベンチマークしていた企業や知り合いの経営者がホールディングス化を実施したという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
近年、中小企業においても注目を浴びており、ホールディングス化を実施した企業は年々増加しております。一方で、ホールディングスという言葉は耳にしたことがあり、興味は抱いているものの、詳細について知らない・ホールディングス化が適しているのか分からない・ホールディングス化後のイメージが沸かない等を、感じていらっしゃる経営者も多いのではないかと思います。
そこで、今回のコラムではホールディングスの基礎知識はもちろん、ホールディングス化を検討する中小企業の特徴、また中小企業におけるホールディングス化のメリット・デメリットを事例を踏まえ、お伝えします。
1.ホールディングス会社とは
ホールディングスとは、英語の「hold(保有)」が語源となっており、ホールディングス会社とは、グループ子会社となる事業会社の株式を保有する親会社を指します。日本語訳は持株会社となり、ホールディングス会社と持株会社は同じ意味を持ちます。
ホールディングス会社には、「純粋持株会社」と「事業持株会社」の2種類が存在します。簡単にそれぞれの特徴をお伝えします。
純粋持株会社とは、主な事業を行わず、事業会社を管理・統括する役割を担っています。事業会社を管理・統括するといっても、親子会社でありながら上下関係が無いのも特徴です。ホールディングス会社における主な売上は、事業会社からの地代家賃・経営指導料・業務委託手数料・配当などです。
ここで、持株会社の歴史をお伝えします。
戦前の日本は三井・住友などの財閥が多数の株式を保有しておりました。これがホールディングス会社の前身とも言われています。しかし、財閥が市場を支配していたため、企業間の競争を平等にできるよう、独占禁止法により持株会社は禁止とされました。時流の変化とともにグローバル化が進み、日本企業の成長のためには持株会社が必要であると判断され、1997年独占禁止法の改定を機に解禁されました。
つまり持株会社の解禁から四半世紀も経っておらず、歴史はまだ浅いということです。当初は売上高1000億円を超える大企業を中心に導入されていましたが、近年では中小企業でも活用されており、中小企業を主要クライアントとする弊社においても売上高20~100億円の企業を主体に相談件数が増加基調にあります。
一方、事業持株会社とは、事業会社を管理・統括しながら、自社においても事業を営む企業です。そのため、ホールディングス会社は、事業会社からの地代家賃・経営指導料・業務委託手数料・配当のみならず、自社の事業における売上もあります。
中小企業においては、オーナー一族が親会社であるホールディング会社の株式を保有し、ホールディング会社が子会社である事業会社の株式を保有するケースが一般的です。
2.ホールディングス会社の役割
それでは、ホールディングスの役割を理解していきましょう。
ホールディングス会社を設立する最大のポイントは、「株式の所有と事業経営の分離」です。すなわち、ホールディング会社と事業会社で、グループ戦略と事業戦略の機能を切り分けることで、意思決定を迅速に行い効率的なグループ経営を図ることができるため、グループ全体をスピーディに成長させる体制を実現することができます。
上記を踏まえて、ホールディングス会社の役割を再度想像してみましょう。
ホールディングス会社は、下記3つの重要な役割を担います。
①グループ会社の全体統括
②グループ投資戦略の立案実行
③事業会社戦略の実行支援
ひとつ事例を出しましょう。
モビリティ事業を営むA社は、社長一族にて3年前にAホールディングス会社を設立し、事業の分社化・M&Aによって、現在6社の事業会社を傘下に置いています。Aホールディングスの経営者は「ホールディングス会社はベンチャーキャピタルだ。」だと仰られました。
なぜベンチャーキャピタルと仰られたのでしょうか。
(ベンチャーキャピタルとは投資を行い出資する会社を指します。さらに、経営コンサルティング・経営支援などを提供し、企業価値向上を図ることも同時に行います。)
Aホールディングス傘下のB社は年商2億円の企業で、会社単体では多額の資金調達が不可能であり、仮に資金調達できたとしても、高金利で行わなければならない状況でした。しかし、グループ全体の経営を担うホールディングス会社が資金調達を行うことで、低金利かつ5億円の資金調達に成功することができました。さらに、Aホールディングスのノウハウを活かすことで、業績も順調に拡大を進めています。
まさに、ホールディングス会社はベンチャーキャピタルのような立ち位置で、3つの重要な役割を果たしているのです。
「社長一族にてホールディングス株式保有=①グループ会社の全体統括」
「事業の分社化やM&Aによる買収=②グループ投資戦略の立案実行」
「ホールディングス会社から事業会社へ資金の貸付=③事業会社戦略の実行支援」
3.ホールディングス化を検討する企業特徴
では、どんな企業がホールディングス化を検討しているのでしょうか。
我々は下記に3つ以上該当する企業へ、ホールディングス化を検討すべきとお伝えしております。
・年商20億円以上
・M&Aを積極的に行いたいと考えている
・複数の事業を展開している
・拠点が複数存在し越境展開している(商圏広域型)
・経営に関与していない株主が存在する(後継者候補除く)
・頼りになる同族外の社員が存在し、社内の内部昇格もしくは外部招聘の検討できる
・関連会社を2社以上有する
しかし、一概には言えません。
そこで、実際に我々がご支援させていただいた企業の共通点をお伝えします。
近年、中小企業のホールディングス化が増えている背景には、更なる成長へ向け実施しているケースが多く存在します。我々はこのようなホールディングスを、「攻めのホールディングス」と呼んでいます。
企業のライフサイクルは、導入期・成長期・成熟期・衰退期の4つに分類され、成長期においては、2つの成長フェーズがあると考えられます。
既存商圏において既存事業のトップシェアを目指し、奔走する「第一フェーズ」、更なる企業成長を目指し、「新規市場の拡大」や「新規事業の参入」を実施する「第二フェーズ」です。
ここでホールディングス化を実施した企業の事例をお伝えします。
住宅不動産業を営むC社は地域トップシェアを確立され、新規出店や同業種であるリフォーム事業等の拡大に注力し、更なる企業成長を目指して、エリア拡大や事業の多角化を構想していました。また、フロー事業である既存業種を考慮し、ストック事業の異業種参入や、M&Aによる水平展開も検討されています。
まさに、第一フェーズから第二フェーズへ突入された企業が、ホールディングス化を検討・実施しているのです。
では次に、ホールディングス化を通して、更なる企業成長を遂げていただきたいからこそ、散見される失敗事例についてご紹介します。
◎次回の内容はこちら
ホールディングス化に関するおすすめ記事

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。