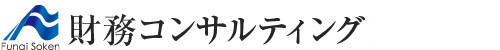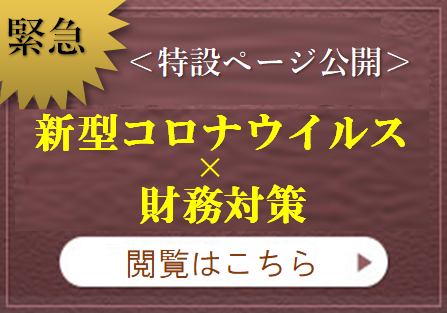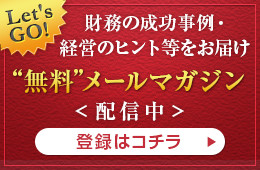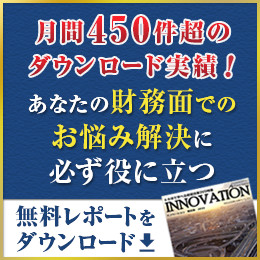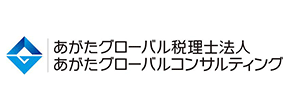2021年はこんな銀行と付き合え金融時流を大予測(1)
- 最終更新日/

「銀行がたくさん融資提案に来るから大丈夫」は大間違い!
今のうちに見直ししないと、来年の融資が厳しい…?
―――――
突然ですが、こんなお悩みはありませんか?
・支店長や担当が変わるたび、また1から関係性を作るのが大変。
・取引している銀行の数が増えて、各行少しずつ態度が異なっている気がする。
・取引している銀行が合併。以前と態度が変わってしまった。
・いわゆる「コロナ融資」で、新たな銀行から融資を受けて取引行が増えた。
・そういえばコロナ以降、あまり来社しなくなった銀行がある。
これらは銀行(信用金庫)と付き合うなかで起きがちな課題もあれば、長引くコロナ市況によって出てきた新たな課題もありますが、どの課題にも共通して言えるのは
自分(自社)の魅力にも気づいていない
からこそ問題が起きるという点です。しかし、なかには上記を問題としてとらえず「とりあえず制度融資でたくさんお金は借りられた」と、さほど気にしていない企業も多い気がします。
しかし、その考えは大間違いで…
・来年、貴社に「しっぺ返し」を与えるかもしれないと知ったら…?
・いま、対策せねば「危ない」かもしれないと知ったら…?
今回は、来年も企業が自社主導で銀行と付き合うためには「いま」何を理解するべきなのか、そのポイントを「銀行理解編」「自社理解編」の2回に分けてお伝えします。
【銀行理解編】「たくさんの銀行と付き合う」の間違い 銀行は選び取る時代
ところで、貴社はいくつの銀行(信金)から融資を受けているでしょうか。
都銀、地銀、政府系金融機関、信用金庫…信金だけでも全国250以上あり、もはや1つだけから融資を受けているという企業の方が少ないかもしれません。
中小企業にとってまず何より大事なのは「資金繰り」であり、たくさんの銀行が貴社に「融資を出しますよ」と営業してくれるのは、資金繰りを安定させる上で心強いものです。
特に不動産、自動車販売、製造、旅館業など常日頃から運転資金や設備資金融資が必要な業種では、
・うちは、メガバンク・大手地銀との融資取引ができている
・5行以上の銀行と付き合い、いつでも案件を相談できる体制が作れている
・融資はないが、しょっちゅう地元の信金さんが営業に来る(から、いつでも借りられる)
など、銀行の規模感や数が多いことが、企業ステータスだと考える社長も多いように感じます。
こうした社長のお話を聞いた際、筆者はいつも等しく
と話すようにしています。というのも、
【銀行取引チェックリスト】
□メガバンクは、年商30億円の壁を超えないと対等な関係で付き合えないことが多い(規模感)
□同じ地銀でも、「貸出残高」に応じて融資の考え方が全く違う(規模感)
□信用金庫は、将来の出店・県外進出について来れない可能性がある(特性)
□「保証協会付融資」だけ出す金融機関とは、正式に付き合っていないのも同然(貸出姿勢)
□「コロナ融資」で新たな取引を始めた銀行は要注意(時流)
など、たくさんの銀行と付き合いできても、詳細な関係性や特徴を調べないことには、企業の融資体制が盤石と言えないことが多いからです。
特に、2020年はコロナウイルスの影響により、銀行も今まで通りに融資を出せる環境ではなくなり、いま一斉に融資姿勢を見直している状況です。
その見直しが終了するであろう2021年になったら?
銀行はますます各々の規模・特徴ごとに複雑に分岐し、社長も「今回もよろしく」と一筋縄でお金を借りられなくなる可能性が高いのです。
10行の銀行が少しずつ貴社を支える体制よりも、自社にメリットがある2つ、3つの銀行と付き合いを深くしていく準備。
それを上記の見直し期間が終わるまでに整備し、見極める時間を設けねばなりません。
まずは、今のうちに最も融資を出してくれている銀行・信金の支店長との面談を設けてみてください。
―――――
◎コラムの続きはこちら

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。