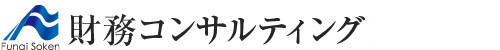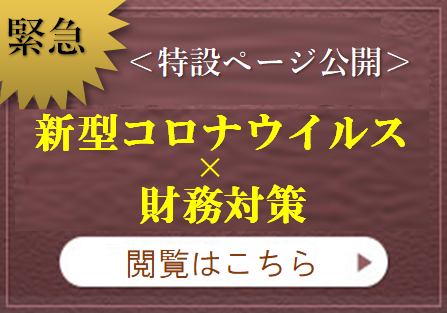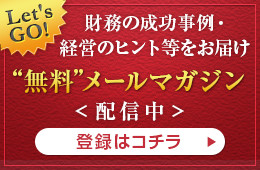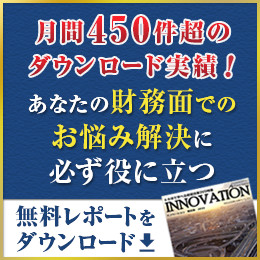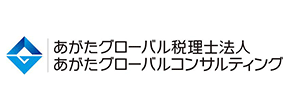自社のおカネは「この指標」で管理!ここから始める財務戦略
- 最終更新日/

まずは「この指標」から経営に導入しませんか?
「自己資本比率が高ければ企業は安定しています」
「借入依存度が〇%を超えないようにしましょう」
財務書籍を買って勉強すると、内容が経営現場で落とし込みにくく、結局どうすれば有効に使えるのかが分かりにくいというお話は、財務の仕事に携わっている筆者もよく聞く話です。
もちろん書籍の知識を完ぺきにマスターすれば、経営に活かせる部分も見えてくるのかもしれませんが、大企業のように財務経理課を置くほどの社員数はおらず、社長自らがトップ営業マンとして活躍しているのが多くの企業の現状で、どうしても「営業優先・財務や管理は二の次」になってしまうことが多いのではないでしょうか。
そもそも財務を重視することで、ちゃんと事業成長にプラスに働くのか?
「財務」というテーマがあまりにも難しそうで、抽象的なばかりにこうした疑問を多数いただくことも多いのですが…こうした皆様には、まず「資金構造」だけでも、まずは現場で把握してほしい…と考えます。
今日は、この「資金構造」に関して焦点を当て、皆様に財務戦略はまずここから始めるべき!というポイントをお伝えしたいと思います。
1にも2にも「資金繰り」から始めよ ~計算式はいらない~
過去のコラムでも何度か財務に関するテーマを扱ってきましたが、その度にいただく感想の中で最も多いのが「財務はとにかく、数字が多くてイメージしにくい!」という内容でした。
それもそのはず、たしかに弊社の財務コンサルタントが扱う指標の多くも計算式ではじき出した、経営がどうなっているかを把握するための理論値に過ぎず、経営者というプロが肌で感じる現場の空気とマッチングしないことが多いから難しいという原因があります。
「貴社は自己資本が多いから良い会社ですって言われても、資金繰りは苦しいけどなあ」
「借入依存度が低いからいいですよって、それは銀行が貸してくれないからそうなっているだけで…」
と出てきた数字だけ眺めても、時には結果が「とんちんかん」なものを導いていることすら、あるかもしれません。
では、財務はやっぱり数字を作る営業の二の次、時間がある裕福な会社だけがやればいいことなのか?
イメージの通り、たしかに財務は分かるようになり、しっかりその指標を管理しても、直接売上UPに貢献し、企業の成長につながる側面は持っていません。
しかし、
・どれだけ安売りして在庫を捌いたとしても、現金の儲けがなければ企業はどんどん貧乏になる
・どれだけ大手とやり取りしても、現金がなかなかもらえない取引ならば苦しい
というように計算式が分からずとも、自己資本比率が何パーセントでも、資金繰りだけはすぐにでも管理できる指標を把握しておかねば、最悪の場合事業継続できなくなってしまう可能性すらあるのです。
であれば、
・自己資金だけでお金を回せる企業なのか?
といった内容を知る指標だけは、押さえるべきということができるのではないでしょうか。
資金繰りは企業の要、ゼニがなくては経営できず。
財務は小難しい計算式ではなく、企業のおカネの問題を点検する有効な戦略と認識できれば最高です。
計算より可視化から 自社の「資金構造」を知ろう
では、財務で見るべき重要な視点やその意義を理解したところで、いよいよ自社の資金繰りに関係してくる財務指標を調査していく基本手法を見ていきましょう。

【表】は、ある企業Zの取引している仕入れ先と、販売先A~C社とのお金のやり取りを日別で可視化したものです。
今回は10日間あたりで企業Zがどのようにお金をもらい、どんなことにお金を使ったかを可視化したのですが、確認してほしいのは、
「企業Zは10日間でA社、B社、C社で70百万円の売上を作ったが、資金は10日間ずっとマイナスだった」
という点です。
それもそのはず、企業Zは商品を売るために当月分の在庫を現金払いで仕入れし、1か月間でその在庫に利益を付けて販売するスタイルをとっているために、期中は延々と収支が赤字になるような状況ということがうかがえます。
また、取引先Cは売上と同時に入金をもらえるので問題ないものの、AやBは売上を立てても翌月まで入金がないため、「勘定あってゼニ足らず」の状況がしばらく継続しています。
企業Zはこの図を確認したら、
・もっと大きな商売をする予定のD社が入ってきたら、どの程度のマイナスになるか?
・仮に仕入れを250百万円にした場合は、10日間で平均いくらのお金がマイナスになるのか?
という視点を持ち、これを金融機関、あるいは社内の資金繰り管理をする際の「資金構造」として把握し、交渉・管理をしなければならないということです。
もう少しレベルアップすると、指標はすべて決算書に掲載されている数値を計算すれば、近似値を得ることも可能になるのですが、それはもっと先の話で問題ありません。
指標を計算できても【表】のような考え方の基本となる部分を把握してこそ、使える財務戦略と言えるでしょう。
簡単なようにも見えますが、ぜひバカにせず1度資金構造の可視化を試してみてはいかがでしょうか。
財務指標も「経営現場」から生まれている
今回は、日々の経営で何となく後手に回ってしまう財務管理に関して、最優先事項は現場の肌感覚を大事にした「資金繰り」を管理することであり、そのためにまずは可視化を用いた自社の資金構造の把握をしてみてはどうかという話をしてきました。
指標の話ばかりを聞いているとだんだん眠くなってしまって…という方でも、取引先名や営業数字との関係性、従業員の声が絡みだすと、その指標が生き生きと経営現場を照らしていることに気づきます。
さあ、ここまでこのコラムではシリーズもので「財務対策」と「事業戦略」を両輪で進めていくことのメリットがあるのか、また「財務」がいかに「事業」と関係性の深い、実はざっくり把握するだけで役立つツールなのかについて、ご紹介して参りました。
お金の悩みから解放されたい経営者様必見!
【このようなお悩みありませんか?】
・資金繰りの見える化をしたい
・大型投資を控えているので良い借入方法を知りたい
・決算対策の方法を知りたい
・コロナ融資を沢山借りてしまった
・銀行との上手い付き合い方を知りたい
自社の財務体制に大きな変革をもたらします!!
───────────────────────────────────
財務対策と事業戦略についての無料相談やお問い合わせも受付ております。
下記よりご連絡ください。
◎メールでのお問い合わせ:
>>https://lp.funaisoken.co.jp/mt/funai-finance/inquiry
◎お電話でのお問い合わせ:
0120‐958‐270 平日9:45-17:30(土日祝除く)
───────────────────────────────────

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。