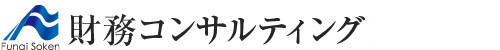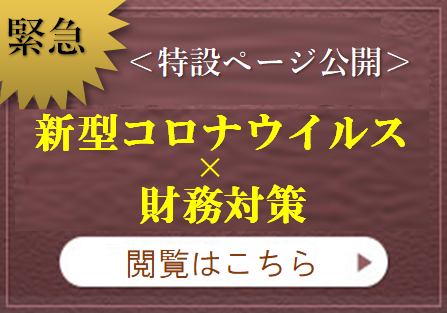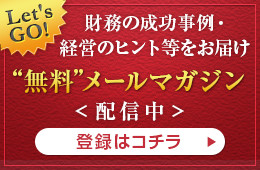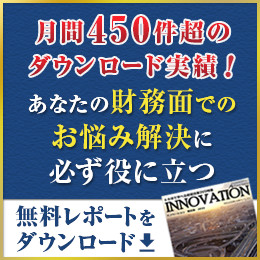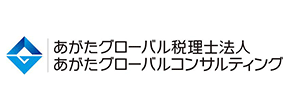金融庁の目利き力、今後の在り方
- 最終更新日/

皆様こんにちは。
金融財務支援部の堀口と申します。
本日は金融庁も問われる目利き力 スルガ銀問題の教訓
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35472660Y8A910C1EE9000/
という記事をピックアップして金融庁に今後の在り方について見ていきたいと思います。
世間を騒がせたスルガ銀行問題。
反省すべきなのは、果たしてスルガ銀行のみなのか。
もちろん監督庁である、金融庁の責任の声も上がる中・・
以下抜粋:
遠藤長官はインタビューで不適切な融資が組織的にまん延していたスルガ銀問題を踏まえた検査・監督のあり方について「自己反省」する姿勢を示した。ではどうすればこの問題を防げたのか。
かつて金融庁は約3年ごとに地銀に立ち入り検査してきた。善しあしは別にして銀行からすれば定期的に金融庁が来るという緊張感があったのは事実だ。ただ定期的に入ると「検査する側も形式的になり、入ったからには成果をあげなければという行動に陥って『重箱の隅をつつく』副作用が大きかった」(遠藤氏)。
このため、ここ数年は特定のリスクに照準を絞って検査を機動的に実施する方針に変えてきた。問題があろうとなかろうと一定の周期で検査に入るより双方に合理的だ。ただしこの運用は、法令順守や利用者保護という最低限のルールが守られているのが大前提だ。
スルガ銀のように順法意識が薄れていた銀行にとっては「試験官のいないテスト」(金融庁幹部)のような状況になりかねないリスクもはらむ。ターゲットから外れれば長期間、検査を受けない地銀もでてくる。このため金融庁内には“銀行性悪説”に立ち、かつてのように定期的に検査することで抑止力を高めるべきだとの声も根強い。
私が金融機関に勤めていた時も「〇〇銀行に金融庁が入った」、「昔来たときは本当に大変だった」と銀行内のみならず、他行の知り合いからもそういった声が聞こえるようになりました。
ドラマ半沢直樹では密に金融庁との関わりがクローズアップされていましたが、最近は上記にも書かれている通り、特定のリスクに絞って検査を行っていることから以前よりは緩くなったという声も聞こえるようになってきました。
以下抜粋
そのために日常の金融機関との対話に加えて見逃せないのが、預金や融資に関するものだけで毎年1万件以上寄せられる利用者からの相談だ。玉石混交だが、スルガ銀問題しかり、過去の多くの金融不祥事は、金融庁の相談窓口に何かしらの情報が寄せられているケースが多いという。
遠藤氏も「寄せられた相談の感触を踏まえて、もう1歩、2歩進んでいけるかどうかは、我々の『目利き』だ」と話す。相談の点と点をつないで、いかに問題を立体的にとらえ、効率的なタイミングで検査に入れるか。スルガ銀問題は金融庁の検査や監督、情報収集のあり方にも重い課題を投げかけている。
今の時代だからこそ問われる金融庁の目利き力が大事になってきます。
後の絶たない不祥事を根本から食い止めるためには、この目利き力がものをいってくる時代になると思います。
毎月のように重なる不祥事・・・
お金を扱う仕事だからこそかもしれません。
お客様の信用、信頼で成り立っている金融業界。
そこに関わる一員として注目してみていきたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。