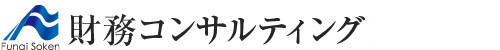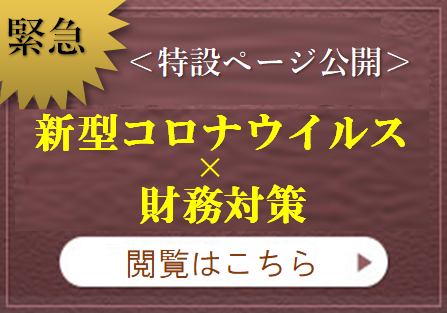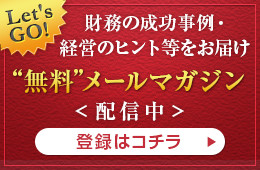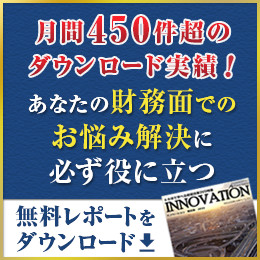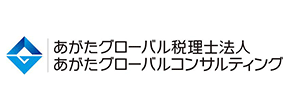コロナ後の緊縮金融に備える財務戦略!~金融機関と友好な関係性を築く情報開示とは?~
- 最終更新日/

「コロナ後の緊縮金融に備える財務戦略! 」と題したこのメールでは、全4回に分けて、コロナ後を見据えた財務戦略のポイント「情報開示」についてお伝えしていきます。
第1~2回目では、コロナ後の緊縮が想定される「金融機関時流」、またその際に必要となる「事業計画見直しの重要性」、について解説しました。
連載第3回目は、「金融機関と友好な関係性を築く情報開示とは?」についてお伝えします。
情報開示と聞くとどのようなことをイメージされるでしょうか?
・決算書や試算表を提出する
・受注明細を提出する
・経営方針発表会の資料を提出する
これらどれもが正解と言えます。
例えば、人材採用をする際には、ホームページや求人広告などの媒体に会社の情報を出されているかと思います。
良い人材を獲得するために、求職者が働きたいと思える要素をしっかりと情報として伝えることが重要です。
同様に、融資を希望する際には、銀行に「この会社に融資したいな」と思われるために自社の良さや特徴をしっかりと知ってもらうことが重要になります。
ポイントとしては、
①数字で説明する
②過去だけでなく、未来の数字を伝える
③B/SやCFの予測も伝える
このような点がポイントになります。上場企業であればまだしも、中小企業でもそこまでする必要があるのかという方もいらっしゃるかと思います。
多くの経営者がそのように考えているからこそ、そこまですることによって差別化を図れると言えます。
もちろん、会社の状況によってはそこまで凝った資料を作る必要もないですが、
・積極的に投資したい
・コロナ騒動後はM&Aも展開していきたい
このように考えている企業であれば、少なからず銀行からの資金調達が必要になるため、友好な関係性を日頃から築いていくことが重要です。
良い話がきてから動くのではなく、良い話がくるまえに準備をしておく。
この考えを実践していくためにも、実は情報開示は有効な手段と言えます。
また、情報開示を通じて銀行が自社に対して考えていることやどのような目線で見ているのかこのような点を知る手段としても活用可能です。
そこで次回は、「情報開示の好事例」を紹介し具体例を通して情報開示による効果をお伝えしていきたいと思います。
◎次回、第4回目「不況下でも一人勝ちする情報開示の好事例」は、こちらから

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。