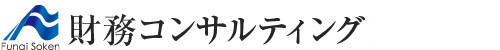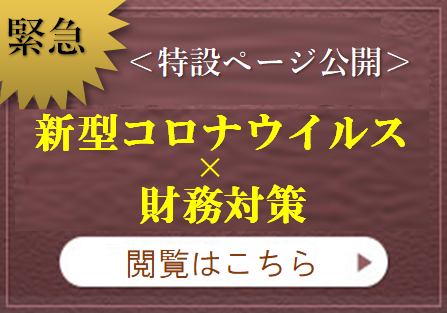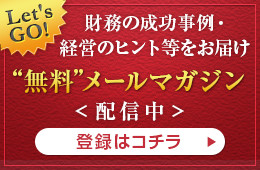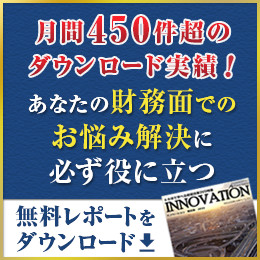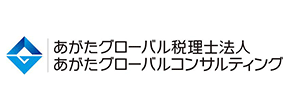外貨建て融資から見る地方銀行の実態
- 最終更新日/

皆様こんにちは。
船井総合研究所金融財務支援部の堀口と申します。
今回は地方銀行の外貨建て融資の記事をピックアップし、現状の地方銀行の実態について詳しく見ていきたいと思います。
先日の日本経済新聞に東京に支店を置く地方銀行が外貨建て融資の貸出額を増加させており、地方銀行全体の東京拠点では1.6兆円と3年で3割増加しているとの記事が日本経済新聞に記載されていました。
こちらの言葉は地方銀行の厳しい現状を示していると思います。
特に地方では新規参入での金利競争が活発化し、利ざやも取れなくなっている。
0コンマ3、0コンマ4……
これはいわゆる0%台の融資ということをさしています。
各銀行にも〇.〇%以下の融資は儲からないといったような指標が存在します。
特にマイナス金利が導入されて以降はこの指標を下回っても融資を実行する機会が多くなっています。
地方で収益が取れない分、東京で上場企業向けの協調融資で運用し収益を確保しているという地方銀行が多いです。
上述の通り、地域融資での収益は底が見えつつある状況です。
ある地方銀行では市内の店舗の法人課を1店に集約するということも実施されるなど店舗の統合化が加速しています。
今後はその状況にさらに拍車がかかることが予想されます。
東京での運用は地方銀行の収益の大きな柱です。
しかし、今回ピックアップした海外企業の中には信用度を裏付ける格付けを持たない企業も多い。
(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32265900W8A620C1EA1000/)日本経済新聞電子版より引用
焦げ付きが予想されるなど、地方銀行にとっては大きなリスクを背負うことになります。
今後はメガバンクと地方銀行が連携してリスクを抑える施策を議論することも必要になってくるのではないかと私自身思います。
地方銀行の収益構造の見直しはこれからさらに本格化するのではないかと思います。
引用:日本経済新聞電子版より
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32265900W8A620C1EA1000/

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。