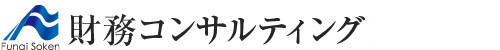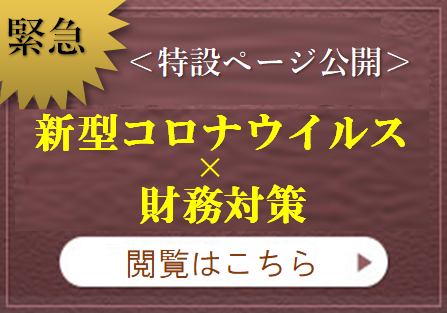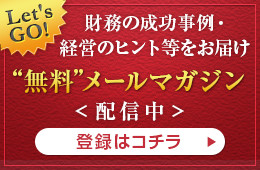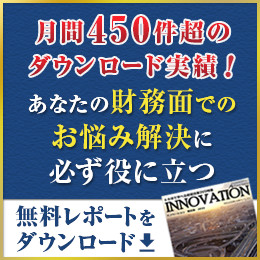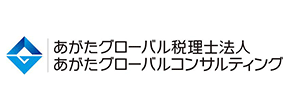◤IT導入補助金活用で導入コストが3分の1! ~クラウド会計導入による月次決算早期化と業務効率化~
- 最終更新日/

2022年に経理業務が大転換!!?
いつもコラムをお読み頂きましてありがとうございます。
突然ですが、「2022年から経理業務が大転換」することをご存知でしょうか。
「経理業務」と聞くと、
・タイムリーに業績が把握できない
・月次決算の精度が低く、数字が合っているのかわからない
・顧問税理士に何度か言ったことはあるが、原因はいろいろあるようで改善が進まない
・決算対策や投資判断、賞与支給、販促投資などが勘頼み
・試算表提出ができず資金調達に悪影響…
等、様々なお悩みを抱える経営者の方が多いかと思います。
ただ、「経理速度は早くはないが遅くもないし、精度もそこそこなのでこのままでも問題ない」とお考えの経営者の皆様、「2022年から経理業務が大転換」するのです…!
2022年1月 電子帳簿保存法の改正
2023年10月 インボイス制度の導入
により、紙中心から電子中心の経理スタイルへ移行する必要があります。
電子帳簿保存法の改正のポイント
電子帳簿保存法の改正のポイントとしては4点あります。
①承認制度の廃止
改正前:導入の3ヶ月前までに税務署まで申請が必要
改正後:基準を満たした準備ができ次第対応可能
②タイムスタンプ要件の緩和
改正前:スキャナ読み取り後、受領者が自署したうえで3営業日以内のタイムスタンプ付与
改正後:スキャナ読み取り時の受領者の署名が不要に。タイムスタンプの付与期間が最長2ヶ月以内に延長
③適正事務処理要件の廃止
改正前:定期検査と相互けん制の適正事務処理要件の対応が必須(定期検査では原本とデータの突合作業が必要)
改正後:要件が廃止され、紙原本の保存が不要に
④検索要件の緩和
改正前:取引年月日、勘定科目、取引金額や帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できることが必須
改正後:検索要件が年月日・金額・取引先のみに
では、この流れに備えるために経営者は何をすべきなのでしょうか?
この流れに備えるために経営者がすべきこと、それは、「クラウド会計」の導入です。
会計ソフト市場におけるクラウド会計のシェアは、現状17%ですが2024年には55%になると言われています。
クラウド会計導入で実現できることとしては、
・自社で月次決算ができる•試算表を10日以内に完成できる
・間接部門の工数や経費を削減できる
・事業拡大をしても経理業務の負荷を軽減できる
・事業所毎で一定の経理業務ができるように分業できるため、事業所を増やしやすくなる
・経理業務が誰でもできるように仕組み化されるため、特定の担当者への属人化を脱却できる
等です。
次に実際にクラウド会計を導入した企業の事例を紹介します。
下記は年商20億円の自動車販売店がクラウド会計を導入した事例です。
〇月次試算表完成までの期間
30日→5日
〇経理人員
2人→1人
〇経理の残業
月末月初→なし
〇粗利率
25%→29%
〇営業利益率
3%→6.5%
事例企業からはクラウド会計の導入により、
・長年進まなかった経理の引継ぎができた
・経営幹部の数値意識が高まった
・顧問税理士の経理や業務の理解が深まった
というお声をいただいています。
年商3億を超え、今後10億、20億と企業規模拡大を目指している企業にとってクラウド会計の導入は必須と言えます。
なぜ今クラウド会計の導入がおすすめなのか?
クラウド会計の導入にあたり現在IT導入補助金を活用することが可能となっております。
IT導入補助金とは、中小企業の課題やニーズに合ったITツール導入の経費の一部を補助する補助金であり、IT導入補助金の活用ができると、最大でクラウド会計導入支援の2/3の補助金を受けることができます。
補助金が活用できる今だからこそ、クラウド会計の導入をお薦めしたいと思っております。
まとめ
如何でしたでしょうか?
2022年1月電子帳簿保存法の改正、2023年10月インボイス制度の導入により経理スタイルの大きな変化が起こります。紙中心の経理スタイルでは業務が煩雑化してしまうため、2022~23年に経理スタイルのデジタル化・クラウド化を進める必要があるのです!
クラウド会計導入はただ経理業務を効率化するだけでなく、成長していく企業の素早い意思決定を助けるためのツールでもあります。
また、現在はIT導入補助金を活用したクラウド会計導入のサポートをさせていただくことも可能です。
年商3億円を超え、経理業務の効率化やリアルタイム経営を実現したいと考えている経営者様は是非一度ご相談くださいませ。
お読みいただき、ありがとうございました。

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。