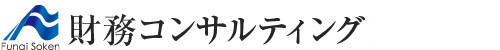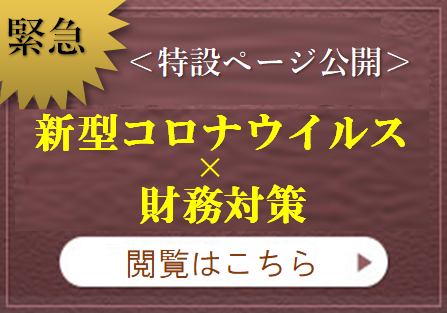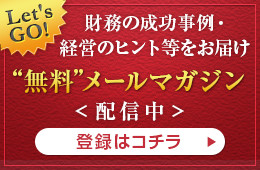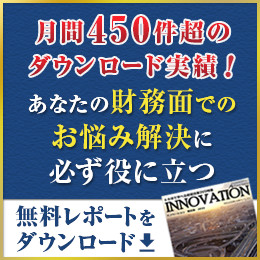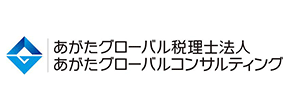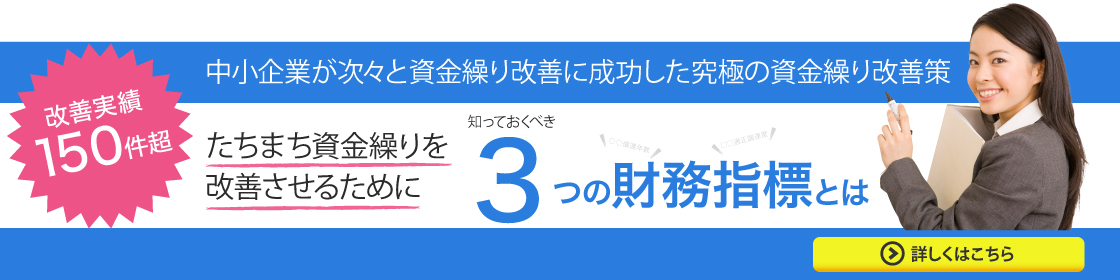財務面からの決算対策とは
- 最終更新日/

これから「決算対策」をテーマにコラムを配信してまいります。
宜しくお願い致します。
「決算対策って実際何をすればいいんだろう」
「節税対策だけしてればいいの?」
「資金調達のための決算対策がわからない」
皆様も、このようなことで頭を悩ませているのではではないでしょうか。
決算対策には、節税を目的とした税務対策と資金調達を目的とした財務対策という視点があり、
実は、税務対策と財務対策の両方の観点から決算対策を考える必要があります。
「税務対策はしてるけど、財務対策はしていない」という経営者様に、
なぜ財務対策が必要なのか、今回は銀行からの資金調達の観点からお伝えしたいと思います。
資金調達について
資金調達手段の代表例である、銀行は融資を検討する際、
純資産の比率(=自己資本比率)や額を見ることで、安全性を確認し、融資判断するケースが多くあります。
節税対策が上手くいっている企業の多くは、損益計算書(P/L)の当期利益がほぼゼロ、
若しくはマイナスとなっており、この当期利益が貸借対照表(B/S)の純資産と連動しているため、
純資産もほとんど増えないか、マイナスとなるような変化をしていきます。
その為、節税が上手くいっている企業は安全性が乏しいケースが多く、資金調達が上手くいかないことや、
出来たとしても高い金利や担保保証がないと資金調達が出来ない、
あるいは業績が落ち込んだ時に一気に資金調達が渋られるといった結果になる可能性が高くなります。
結果として、金利面のコスト負担や成長にかけるための資金調達が出来ず
収益力の低下や成長が鈍化、極端な場合、資金調達が出来ず倒産となることも想定されるのです。
節税ばかりに視点が行ってしまうと、本業に支障をきたしてしまう可能性があり、
会社としての信用力を高めていくための財務(銀行)目線での決算対策も必要となります。
目指すべきB/Sを意識した経営や、自己資本比率の目標値を設定しそれを実現するまでは、
節税を抑制するなどといった対策を講じるのも有効です。
現在の財務状況や今後の経営方針などを踏まえて、
税務対策と財務対策のどちらに傾注すべきなのかを考え
「決算対策」に取り組んでいただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。

船井総研の財務コンサルティングは、企業の業績アップを「資金と管理面」からバックアップする実行型コンサルティングです。
財務指標をただ算出してその上下を評価するのではなく、それらの指標をどのように経営判断、投資判断材料とするのか、持続的な成長を支える為に必要な資金調達額を最大にするための施策を検討、実行します。
攻めの投資を実現する際に最も大切なことは、その1期のみ最大の成果を出せることではなく、持続的に最大限の成長を継続することです。
それを資金面から実現する戦略をデザインします。